×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
どれだけ久しぶりなんだ、というよりは
更新すること自体が奇跡のような状態になっており申し訳ないです。
先月のヘッドフォン祭熱が冷めぬうちに書こうと思っていた
E17についても、気付けば購入から1ヶ月も過ぎてしまいました。
というわけで、やっとE17について語ろうと思います。
当初は購入時レビューで済まそうと思っていたところ、
この1ヶ月みっちりと使い込んだので
じっくりとレビューさせていただきます。
<基本情報>
メーカー公式の測定値などは
公式ページ(http://www.oyaide.com/fiio/e17.html)をご覧ください。
ご購入はAmazon等の通販サイトや家電量販店にて。
参考:Amazon(一般販売)、Amazon(並行輸入)
※並行輸入の場合、価格が安い代わりに日本語マニュアルが無い、
サポートが代理店依存といった点があります。
Fiioとしては、もともとハイエンドモデルとしてE7があったわけですが、
E17はその正統上位機種となります。
E7ではデジタルインプットがUSBのみでしたが、
E17では光デジタル(コアキシャル・オプティカル)にも対応、
ソースは192kHz/24bitまで対応できるようになりました。
<使用感~E7と比較も兼ねて>

(左:レビュー対象のE17、右:下位モデルのE7)
もともと、ポータブルアンプとしてE7を使っていたので
使用感ともども、比較対象としてもってこいかと思います。
E7からのアップグレードをお考えの方は是非参考にしていただければ。
<アナログアンプとしての性能>
インプットにはKENWOOD HD60GD9(Sound Meister Editon)を使用しています。
本体下部に3.5mmジャックのアナログインプットがあります。
これはE7の時と同じです。
多くのポータブルアンプがインプット・アウトプットが同じところにあるので
インが下部、アウトが上部にあるE7やE17を使いにくい、と思う人もいるようです。
実際のところ、特にアンプに限れば頻繁に操作するわけでも、
ケーブル接続をいじるわけでもないので、気にならないレベルとは思いますけどね…
スルーアウトとしての音質は可もなく不可もなく、というものです。
もともとアナログの場合はインプット側のアンプ性能に依存するので
この機種につないだことで劇的に音質が向上する、ということはありません。
よって多くのアナログアンプは、あくまで「色を変える」ものですが、
E17は音量以外についてはほぼそのままダイレクトに出力していると
思ってもらって構いません。
厳密に聴けば、E7だと若干音が細い、
よく言えば繊細、悪く言えば痩せた感じに聴こえますが、
E17はそういった「インプットからの差異」がほとんど感じられない、
といったほうが正確でしょうか。
大型ヘッドホンに対するドライブ力は?という点については
そもそも3.5mmのインプットでは情報量に限界があるので
例えばedition9を繋いでもちゃんと音が鳴るのか?といわれても
そもそもedition9の表現を出しきれるインプットではないので
比較することは困難かと思います。
以前E7をレビューした時にも述べた気がしますが、
Fiio製品を使う最大の恩恵は低音イコライザーを使用した時と言えます。
<イコライザーの効果>
E7では低音のみ3段階のイコライザーを設定できましたが、
E17は低音(BASS)と高音(TREBLE)を11段階で設定できます。
目盛は±10ありますが、実際は2段階で推移するため、
減衰5段階、増幅5段階とスルーアウト(ゼロ)といえます。
増やせる周波数帯(Frequency)は選べません。
特に低音について言えば、E7でも「ふざけているのか!?」というくらい
爆低音になって、最大だと普通のヘッドホンでは音割れしてしまうレベルでしたが、
E17の低音もすさまじい増やし方になっています。
E7の最大値(BASS3)=E17の「+8」と「+6」の中間といったところです。
「ふざけているのか!?」レベルよりもさらに上があります。
多くのヘッドホンはBASS+6で音割れが始まります。
edition8レベルだと、BASS+10でもちゃんと鳴らせますが、
もうここまでくるとベースプレイヤーにでもなったのか?というくらい低音しか聞こえません。
ただ、E7の時もそうだったのですが
この低音増幅の仕方が非常に上手なのがFiioの特筆すべき点です。
大抵こういった類の大雑把なイコライザは、増やすと余計な周波数帯も増えて
音が呆けるか、高音なら音がシャリつくという弊害を招くものですが、
Fiioの場合、聴きたい低音だけガッツリ上げてくれるという音になります。
ボーカルや伴奏はそのままに、ベースの音だけ思いっきり前に来る、
ただ単に増幅させて輪郭のボケた低音ではなく、動きも像もキビキビした低音で、
私はこの点でFiio製品は非常に高く評価しています。
E17においても、この点はしっかり守られており、
正直edition8で聴く分には、低音マニアな私には
ソース如何では+10でもまったく問題ありません。
非常に質の良い低音を聴かせてくれるのです。
実際のところ、普段使用に於いてはBASS+8を使っています。
低音のドライブが上手なedition8に、低音出力の上手なE17は最高の相性です。
<DACとしての性能>
インプットには据え置きのオーディオインターフェース(MOTU 828mkII)を使用しています。
※E17はiPadへの接続ができなくなりました。

E17では、前述の通り、USB以外にオプティカル・コアキシャルにも対応しました。
端子は本体上部の3.5mmジャックで、
コアキシャルの場合は付属の変換端子(下側の端子)を噛ませて使い、
オプティカルの場合、丸型端子はそのまま3.5mmジャックに接続可能、
角型端子(TOS-LINK)は付属(上側の端子)または市販の変換端子で接続できます。
192kHz/24bitのインプットまで対応できるようになったのですが、
残念ながら私の所有する音源は96kHz/24bitが上限なのでソースはその規格となります。
実際に鳴らしてみると、これがなかなか素晴らしい。
正直「2万円程度のDACなんか使い物にならない」と思っている人もいると思いますが
DACとしての性能は高級機にヒケを取らないといえるでしょう。
価格を知らなければ10万円クラスのDACといわれても通用するサウンドです。
もう少し具体的にいえば、やや高音成分が強く、
ソースや使用する機器によっては耳に刺さる感はあるかもしれません。
また、スルーアウト状態だとやや低音成分が弱く、肉厚さという点ではやや弱い気がします。
それでも、音の距離感は明確に表現されており、
動きも明瞭でキビキビとしたサウンドです。
肉厚さに不満を感じる方は、BASSを+2か+4にすることで若干改善されると思いますが
特にボーカル部分の周波数帯や木管楽器の音域までは増幅されないので
音の豊潤さを求める人には、かなり好みを選ぶ可能性があります。
それでなくても、この価格帯、あるいはこのサイズでは
あり得ないほどの高音質、高品質であるといえます。
おそらくこの機種以上のものを求めるなら、
ポータブルDACではなく据え置きのDACが必要でしょうね。
<その他の使用感について>
・操作パネル
E7の側面から、前面にパネルが配置されました。
これは一長一短で、使う人によっては操作しやすくなった、
逆に操作しにくくなったという人がいると思います。
特に、ポータブルアンプだとバンドなどでDAPと結束している人も多く、
その用途の人にはちょっと面倒かもしれません。
・ディスプレイ
E7で気になっていた付けっぱなしの有機ELですが、
E17の場合も基本常時点灯でありながら、
「hold」スイッチを入れることで表示も消えるようになりました。
・バッテリー継続
これが今回E17で最も手痛いところで、
メーカー公表は「連続15時間」となり、E7の「連続80時間」から大幅に減りました。
この値は、使っている分には妥当か、実際はもっと短いかもしれません。
通勤用途では週1回の充電で済んでいたE7も、
E17だと3日間ぐらいで充電の必要があります。
・E9連携

E9互換のドックコネクタを搭載しており、
E7同様にE9へ接続することができます。
その際は、E17のDACを利用してE9のUSB端子を使えるようになるのも同じです。
E9の電源を入れれば、自動的にE17への充電が行われます。
E7の時もそうだったのですが、接続することでE9のUSB端子が使えるわけですが、
機能的にE17(E7)と連動しているわけではなく、
イコライザ機能などの設定は反映されません。
また、音質もE9のアンプ出力に依存しているためか、
E7からE17に変えたことでの音の変化は、体感的にはありませんでした。
<まとめ>
総合的には、E7から正統進化をしており、
マイナスなのはバッテリー持続時間、および
iPadへのUSB接続が出来なくなった点だけと思って良いです。
(E7は、以前当blogでも取り上げた通り、iPad接続をウリにしていたこともあり、
人によってはこの部分が大きい場合もあるかもしれません…)
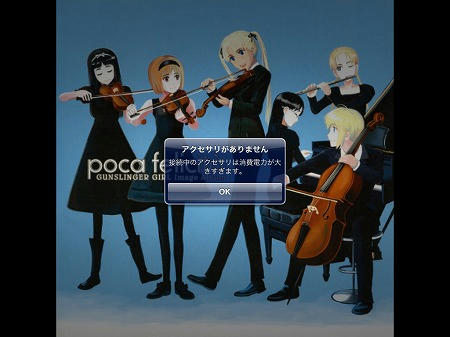
(iPad接続時に表示されてしまうエラー。音もE17からは出ない)
ポータブルアンプとしてはサイズ、重量ともに適切で
価格が2万円台という中堅価格帯ながら、
性能は高性能DACにヒケを取らないというコストパフォーマンスにも優れています。
やや高音寄り、繊細な音作りではありますが、
イコライザによってある程度自分の好きな音に変えることもできますし
(そのイコライザ機能こそ、E17やFiio製品の醍醐味かと)
安価に良いDAC機能を求める人、
あとはイコライザいじるくらいに低音大好き人間には是非に、
といった感じです。
<蛇足>
ヘッドホン的な話題はあまりネタが無いのですが、
ヘッドホン以外の音響関係のネタが結構あったりするのです。
次回更新はまたいつになるかわかりませんが、
あまりにもネタが無ければ、そっち方面もちらっと紹介しようかな、などと画策中です。
期待せずに、お楽しみに。。。
メーカー公式の測定値などは
公式ページ(http://www.oyaide.com/fiio/e17.html)をご覧ください。
ご購入はAmazon等の通販サイトや家電量販店にて。
参考:Amazon(一般販売)、Amazon(並行輸入)
※並行輸入の場合、価格が安い代わりに日本語マニュアルが無い、
サポートが代理店依存といった点があります。
Fiioとしては、もともとハイエンドモデルとしてE7があったわけですが、
E17はその正統上位機種となります。
E7ではデジタルインプットがUSBのみでしたが、
E17では光デジタル(コアキシャル・オプティカル)にも対応、
ソースは192kHz/24bitまで対応できるようになりました。
<使用感~E7と比較も兼ねて>
(左:レビュー対象のE17、右:下位モデルのE7)
もともと、ポータブルアンプとしてE7を使っていたので
使用感ともども、比較対象としてもってこいかと思います。
E7からのアップグレードをお考えの方は是非参考にしていただければ。
<アナログアンプとしての性能>
インプットにはKENWOOD HD60GD9(Sound Meister Editon)を使用しています。
本体下部に3.5mmジャックのアナログインプットがあります。
これはE7の時と同じです。
多くのポータブルアンプがインプット・アウトプットが同じところにあるので
インが下部、アウトが上部にあるE7やE17を使いにくい、と思う人もいるようです。
実際のところ、特にアンプに限れば頻繁に操作するわけでも、
ケーブル接続をいじるわけでもないので、気にならないレベルとは思いますけどね…
スルーアウトとしての音質は可もなく不可もなく、というものです。
もともとアナログの場合はインプット側のアンプ性能に依存するので
この機種につないだことで劇的に音質が向上する、ということはありません。
よって多くのアナログアンプは、あくまで「色を変える」ものですが、
E17は音量以外についてはほぼそのままダイレクトに出力していると
思ってもらって構いません。
厳密に聴けば、E7だと若干音が細い、
よく言えば繊細、悪く言えば痩せた感じに聴こえますが、
E17はそういった「インプットからの差異」がほとんど感じられない、
といったほうが正確でしょうか。
大型ヘッドホンに対するドライブ力は?という点については
そもそも3.5mmのインプットでは情報量に限界があるので
例えばedition9を繋いでもちゃんと音が鳴るのか?といわれても
そもそもedition9の表現を出しきれるインプットではないので
比較することは困難かと思います。
以前E7をレビューした時にも述べた気がしますが、
Fiio製品を使う最大の恩恵は低音イコライザーを使用した時と言えます。
<イコライザーの効果>
E7では低音のみ3段階のイコライザーを設定できましたが、
E17は低音(BASS)と高音(TREBLE)を11段階で設定できます。
目盛は±10ありますが、実際は2段階で推移するため、
減衰5段階、増幅5段階とスルーアウト(ゼロ)といえます。
増やせる周波数帯(Frequency)は選べません。
特に低音について言えば、E7でも「ふざけているのか!?」というくらい
爆低音になって、最大だと普通のヘッドホンでは音割れしてしまうレベルでしたが、
E17の低音もすさまじい増やし方になっています。
E7の最大値(BASS3)=E17の「+8」と「+6」の中間といったところです。
「ふざけているのか!?」レベルよりもさらに上があります。
多くのヘッドホンはBASS+6で音割れが始まります。
edition8レベルだと、BASS+10でもちゃんと鳴らせますが、
もうここまでくるとベースプレイヤーにでもなったのか?というくらい低音しか聞こえません。
ただ、E7の時もそうだったのですが
この低音増幅の仕方が非常に上手なのがFiioの特筆すべき点です。
大抵こういった類の大雑把なイコライザは、増やすと余計な周波数帯も増えて
音が呆けるか、高音なら音がシャリつくという弊害を招くものですが、
Fiioの場合、聴きたい低音だけガッツリ上げてくれるという音になります。
ボーカルや伴奏はそのままに、ベースの音だけ思いっきり前に来る、
ただ単に増幅させて輪郭のボケた低音ではなく、動きも像もキビキビした低音で、
私はこの点でFiio製品は非常に高く評価しています。
E17においても、この点はしっかり守られており、
正直edition8で聴く分には、低音マニアな私には
ソース如何では+10でもまったく問題ありません。
非常に質の良い低音を聴かせてくれるのです。
実際のところ、普段使用に於いてはBASS+8を使っています。
低音のドライブが上手なedition8に、低音出力の上手なE17は最高の相性です。
<DACとしての性能>
インプットには据え置きのオーディオインターフェース(MOTU 828mkII)を使用しています。
※E17はiPadへの接続ができなくなりました。
E17では、前述の通り、USB以外にオプティカル・コアキシャルにも対応しました。
端子は本体上部の3.5mmジャックで、
コアキシャルの場合は付属の変換端子(下側の端子)を噛ませて使い、
オプティカルの場合、丸型端子はそのまま3.5mmジャックに接続可能、
角型端子(TOS-LINK)は付属(上側の端子)または市販の変換端子で接続できます。
192kHz/24bitのインプットまで対応できるようになったのですが、
残念ながら私の所有する音源は96kHz/24bitが上限なのでソースはその規格となります。
実際に鳴らしてみると、これがなかなか素晴らしい。
正直「2万円程度のDACなんか使い物にならない」と思っている人もいると思いますが
DACとしての性能は高級機にヒケを取らないといえるでしょう。
価格を知らなければ10万円クラスのDACといわれても通用するサウンドです。
もう少し具体的にいえば、やや高音成分が強く、
ソースや使用する機器によっては耳に刺さる感はあるかもしれません。
また、スルーアウト状態だとやや低音成分が弱く、肉厚さという点ではやや弱い気がします。
それでも、音の距離感は明確に表現されており、
動きも明瞭でキビキビとしたサウンドです。
肉厚さに不満を感じる方は、BASSを+2か+4にすることで若干改善されると思いますが
特にボーカル部分の周波数帯や木管楽器の音域までは増幅されないので
音の豊潤さを求める人には、かなり好みを選ぶ可能性があります。
それでなくても、この価格帯、あるいはこのサイズでは
あり得ないほどの高音質、高品質であるといえます。
おそらくこの機種以上のものを求めるなら、
ポータブルDACではなく据え置きのDACが必要でしょうね。
<その他の使用感について>
・操作パネル
E7の側面から、前面にパネルが配置されました。
これは一長一短で、使う人によっては操作しやすくなった、
逆に操作しにくくなったという人がいると思います。
特に、ポータブルアンプだとバンドなどでDAPと結束している人も多く、
その用途の人にはちょっと面倒かもしれません。
・ディスプレイ
E7で気になっていた付けっぱなしの有機ELですが、
E17の場合も基本常時点灯でありながら、
「hold」スイッチを入れることで表示も消えるようになりました。
・バッテリー継続
これが今回E17で最も手痛いところで、
メーカー公表は「連続15時間」となり、E7の「連続80時間」から大幅に減りました。
この値は、使っている分には妥当か、実際はもっと短いかもしれません。
通勤用途では週1回の充電で済んでいたE7も、
E17だと3日間ぐらいで充電の必要があります。
・E9連携
E9互換のドックコネクタを搭載しており、
E7同様にE9へ接続することができます。
その際は、E17のDACを利用してE9のUSB端子を使えるようになるのも同じです。
E9の電源を入れれば、自動的にE17への充電が行われます。
E7の時もそうだったのですが、接続することでE9のUSB端子が使えるわけですが、
機能的にE17(E7)と連動しているわけではなく、
イコライザ機能などの設定は反映されません。
また、音質もE9のアンプ出力に依存しているためか、
E7からE17に変えたことでの音の変化は、体感的にはありませんでした。
<まとめ>
総合的には、E7から正統進化をしており、
マイナスなのはバッテリー持続時間、および
iPadへのUSB接続が出来なくなった点だけと思って良いです。
(E7は、以前当blogでも取り上げた通り、iPad接続をウリにしていたこともあり、
人によってはこの部分が大きい場合もあるかもしれません…)
(iPad接続時に表示されてしまうエラー。音もE17からは出ない)
ポータブルアンプとしてはサイズ、重量ともに適切で
価格が2万円台という中堅価格帯ながら、
性能は高性能DACにヒケを取らないというコストパフォーマンスにも優れています。
やや高音寄り、繊細な音作りではありますが、
イコライザによってある程度自分の好きな音に変えることもできますし
(そのイコライザ機能こそ、E17やFiio製品の醍醐味かと)
安価に良いDAC機能を求める人、
あとはイコライザいじるくらいに低音大好き人間には是非に、
といった感じです。
<蛇足>
ヘッドホン的な話題はあまりネタが無いのですが、
ヘッドホン以外の音響関係のネタが結構あったりするのです。
次回更新はまたいつになるかわかりませんが、
あまりにもネタが無ければ、そっち方面もちらっと紹介しようかな、などと画策中です。
期待せずに、お楽しみに。。。
PR
この記事にコメントする
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
簡易版機種別ショートカット
※各機種の関連記事にリンクします。
[STAX] 4070
[DENON] AH-D7000(balanced)
[audio-technica] ATH-W5000(balanced)
[audio-technica]
ATH-ESW10JPN
[ULTRASONE] edition9(balanced)
[GRADO] GS1000(balanced)
[GRADO] PS1000(balanced)
[SENNHEISER]
HD800(balanced)
[Victor] HP-DX1000
[AKG] K701(balanced)
[SONY] MDR-SA5000
[STAX] SR-007A
[audio-technica] ATH-ESW9
[STAX] SR-001MK2
[SONY MUSIC] MDR-CD900ST
[STAX] SR-404
[PHILIPS] SBC-HP1000
[HeadRoom] Balanced Home Amp
[STAX] SRM-007tA
[HeadRoom] Portable Micro Amp
[Mark Of The Unicorn] 828mkII FireWire
[PS Audio] Power Plant Premier
[岩井喬(書籍)]
新・萌えるヘッドホン読本(リンク集)
カテゴリー
コメントありがとうございます。
※ 印は管理人返信済みです。
印は管理人返信済みです。
 印は管理人返信済みです。
印は管理人返信済みです。[04/09 Caseyeverm]
[04/01 Dennistip]
[03/15 Williamteata]
[03/11 Galenunede]
[03/08 Richardrisse]
最新記事
(11/25)
(11/06)
(03/22)
(09/08)
(09/07)
リンク(ヘッドホン関係)
ブログ内検索
プロフィール
管理人:
誕生日(年齢):
1983/06/19(42歳)
近況メモ:
2016/11/25 - あっという間に時が流れ、このblogも開設から10年目。2016年はその締めくくりをしたく思っています。2000年代後半にハイエンドの虜になった、一人のマニアの軌跡です。
↓blog管理人直通メール↓
headphone.at.digi@gmail.com
※本blogはリンクフリーですが
事後でも連絡があると嬉しいです。
記事・画像の無断転用は遠慮下さい。
意見質問等はコメントorメールを。
カウンター
アクセス解析
